【試し読み】糸を噛む~死を待つ王女に捧げる仕立て屋の深愛~
あらすじ
「ダメだったら、一緒に死んでやる!」――叔父の裏切りにより、婚姻直前で塔に幽閉された王女レオノーラは、密かに想いを寄せる仕立て屋エドガーに『黒衣』の依頼をする。処刑が決まった王族は、指名した職人と共に、最期の衣装を仕立てるしきたりがあるのだ。一方、依頼を受けたエドガーは、死に直面してなお笑みを崩さず本音を見せない王女に言い知れぬ怒りを抱き、その甘く苦い想いを自覚してしまう。隣国の王太子妃になる彼女と自分が結ばれることはない。それでも――生きてくれているのなら、それでいい。 二人きりの塔で口づけを交わし、仕立て屋は王女を助け出す覚悟を決める。一度きり、命がけの恋の行方は――?
登場人物
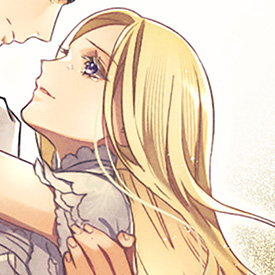
レイアドルの王女。叔父の裏切りにより幽閉され、処刑を待つ身に。

成り上がりの宮廷付き仕立て屋。レオノーラから『黒衣』を依頼される。
試し読み
プロローグ
大陸の北西に位置するレイアドルは、服飾文化によって発展した王国だ。
人口の三分の一が服飾関連の仕事についており、貴族のベストやドレスはもちろん、騎士服や平民の衣服に至るまで、服飾における流行は全てレイアドルから生まれると言われて久しい。
その文化を支えるのは、歴史ある三つの大商会と、そこにそれぞれ所属する三人の宮廷付き仕立て屋だ。
中でも王家の針と糸と呼ばれ、神の手とまで謳われた仕立て屋、ガドリン商会のエドガー・ランハートは平民から成り上がり、一代貴族の称号を得た国民の英雄である。
エドガー・ランハートの爵位授与式が終わった後、王宮の広間では受勲を祝うパーティーが開かれた。
レイアドル国の王女であるレオノーラは、広間の一段高い場所に座りながら、忙しなく視線を動かしてエドガーの姿を捜していた。立場上、あちらこちらと歩き回るわけにはいかないが、どうしても彼の姿をひと目見てみたかったのだ。
だが、レオノーラはそもそもエドガーに直接会ったことがない。爵位授与式にも国の規定で王女は参列できなかった。
巨大なシャンデリアが輝く王宮の広間は、服飾大国レイアドルの名に相応しく煌びやかな衣装を纏う貴族らで埋め尽くされている。その様子はまるで一面の花園で、眺める分には良いが、形も分からぬ花を一輪見つけ出すのは至難の業だ。レオノーラには、誰がエドガーかと目処をつけることすら難しかった。
「ほら、レオノーラ。あの赤のベストが目立っている……、黒いくせっ毛の男がエドガーだよ」
そんなレオノーラを見かねたように、隣に座る兄がくすっと笑って広間の一点を指差した。
視線を向けると、そこでは兄の言う特徴にあった若い男性が貴族らと談笑している。
レオノーラは思わず胸に手を当て、息を呑んだ。
――あれが……。
その手で数々の流行を作り出し、レイアドルの長い歴史のなかでも、最も優れた腕を持つといわれる仕立て屋。
年はまだ二十五歳。
耳にかかる長さの黒髪は柔らかそうなくせ毛で、前髪は紳士らしく後ろに流しており、形のいい額が露わになっている。非常に整った顔をしているが中性的な感じはなく、意志の強そうな眉と、夜の海を思わせる底の知れない黒い瞳が印象的だ。
すらりとした長身と、長い手足はまるで彫像のようにバランスが良く、前面に華やかな金糸の刺繍がはいった黒いコートと、赤いベストを見事に着こなしている。
レオノーラは目を輝かせてその姿に見入った。
胸が激しく高鳴っている。彼をとても素敵だと思った。どんなお伽噺のなかにも、彼より心惹かれる人はいないだろうと。
たとえこの時、レオノーラが彼に強く憧れていなかったとしても、きっと同じことを思ったに違いない。
それは、いまから三年前のこと。
十二歳になったレオノーラは、近く社交界入りすることが決まり、そこで着るドレスをどうするかに頭を悩ませていた。
レイアドルでは、王族の衣服は三大商会に所属する〝宮廷付き仕立て屋〟が用意する決まりになっている。また仕立て屋が担当する王族も一年ごとに変わっていく。
この決まりはレイアドルにある三大商会を平等に扱う為のもので、王族が勝手に贔屓の仕立て屋を指名できないようになっている。
レイアドルで作られたレースの一切れは、時にダイヤモンドよりも価値を持つ。長い間守られてきた服飾文化は、レイアドルの国力そのものなのだ。
だからこそ服飾の製作、流通を担う三大商会の力のバランスは、王家の権威のもと慎重に守られてきた。
しかし、決まりのなかにも例外はある。
王族は生涯において、ある三つの場面でのみ仕立て屋を指名することができる。
その一つが社交界デビューだ。
レオノーラにはこの時、特別に気に入っている仕立て屋がいなかったので、両親の勧めに従って三人の宮廷付き仕立て屋にデザインを依頼し、出来上がったものの中から一つを選ぶことにした。
だがいざ彼らが用意したデザインを見ると、レオノーラの心には迷いが生まれた。
仕立て屋たちが考えたドレスは、どれも黄色やピンク、水色といった淡い色合いで、ふんだんにレースやフリルをあしらっている。
十二歳の少女が着るドレスなのだから可愛らしいデザインなのは当然だが、レオノーラはそのどれもが自分に似合うとは思えなかった。
レオノーラは、同じ年頃の少女よりも大人びた顔つきをしていた。
白金色のまっすぐな髪に、大きな菫色の瞳、丸い頬に、小さな唇。ひとつひとつのパーツは子供らしさを残しているのに、それが小さな輪郭のなかに収まった途端、不思議と大人っぽさを醸し出す。
その為あまり子供らしいデザインのドレスを着ると、まるで前髪を切りすぎた時のようなアンバランスな印象になってしまうのだ。
もう一度依頼をかけ『もっと大人っぽいデザインを』と頼んでみたが、結局は子供用の範囲から出てこない。
当然だ。仕立て屋たちが優先して考えるのは〝レオノーラに似合うドレス〟ではなく、〝レイアドル王女の社交界デビューに相応しいドレス〟なのだから。
十二歳の王女の社交界デビューには大人っぽいドレスより、可愛らしいドレスが似合うのだ。
レオノーラの纏うドレスは王家の品位に直結し、その評判は仕立てた職人の今後を左右する。
だから彼らは決して、〝王家〟の望むドレス以外を用意したりはしない。
レオノーラも、そんなことはよく分かっている。
ただ、がっかりしないわけではないというだけで。
思い返せば、この時のレオノーラはまだ、子供らしい反抗心を残していたのだと思う。用意されたデザインがどうしても気に入らず、中々ひとつを選ばずにいると、侍女のひとりがふとこう言った。
「いま王都では、エドガー・ランハートという仕立て屋がとても評判なのですよ。ガドリン商会の所属で、次の〝宮廷付き〟になるのは彼に違いないともっぱらの噂で……」
レオノーラは「そう」と何でもなさそうに頷いたけれど、内心では強く興味を惹かれていた。
街の仕立て屋なら、〝宮廷付き〟よりも柔軟にデザインを考えてくれるかもしれない。そして次の〝宮廷付き〟にと期待されるぐらいなら、腕も確かだろう。
まずはデザインだけでも見てみたい。レオノーラは「試しに」と前置きをしてから、エドガーにデザインの依頼をした。
その際、エドガーから求められたのはレオノーラの肖像画の貸与と、採寸の情報だけ。
やがて送られてきたエドガーのデザインを見たとき、レオノーラはまるで雷に打たれたような衝撃を受けた。
エドガーが用意したデザインは一枚のみ。
これがただ一つの正解であるとばかりに差し出されたデザインは、すっきりとしたシルエットの漆黒のドレスだった。
見本布は光沢のある黒糸のシルクサテン。これはレイアドルでは成人した女性が好んで使う生地である。リボンやフリルといった飾りは控えめに、代わりに袖や胸元にはふんだんに黒のレースを用いている。
肌の露出こそ少ないが、どう見ても艶やかさを意識して考えられたデザインであり、十二歳の少女のドレスとは思えない。王女の社交界デビューのドレスとしては、あまりに規格外なデザインだ。
この様なドレスを着て社交界に出た日にはいったいどんな評判が立つことか。
そう考えた時、レオノーラの胸にはこれまで感じたことのない高揚感がわき上がってきた。
このドレスを着たレオノーラを見た人は、きっと誰もが最初に息を呑むだろう。
そして次に、レオノーラを賞賛するに違いない。
〝王女の社交界デビューのドレスはこうあるべき〟という常識を覆すほど、このドレスは自分に似合う。レオノーラはそう確信できた。
ひと目見た瞬間から、レオノーラはこのドレスの虜になっていたのだ。
どうしても、エドガーの仕立てたドレスを着てみたい。
レオノーラは彼に仕立てを依頼すると決めた。
父母は反対したけれど、仕立て屋を選ぶ権利は自分にあるからと、生まれて初めて我が儘を通した。
出来上がったドレスは、レオノーラが予想した通りにとても素晴らしい物だった。全体の作りはまさにデザイン通りだし、レースはきめ細かく、裏地も丁寧に処理をされている。
胸を高鳴らせながらドレスに袖を通したレオノーラは、鏡を見てもう一度驚くことになった。
その漆黒のドレスを纏ったレオノーラが、とても少女らしい愛らしさを持って見えたからだった。
レオノーラの髪や肌の色、顔つき、スタイル。ドレスはその全てを見事に活かしていた。
おそらくレオノーラ以外の誰が着ても、これほど似合うことはないだろう。
レオノーラはただただ、鏡のなかの自分に釘付けになった。
そこに映るのは〝レオノーラ王女〟ではなく、〝レオノーラ・レイアドル〟という一人の人間の姿だ。
エドガーの仕立てたドレスが、これまで世界のどこにもいなかった〝レオノーラ〟の輪郭をこの世に浮き上がらせたのだ。
この世界でただ一人、エドガーだけがレオノーラを見つけてくれた。
それはレオノーラにとって、まるでこの世に生まれ直したような衝撃で、エドガーに強い憧れを抱くには十分すぎる理由だった。
ドレスはレオノーラに似合うだけでなく、高貴さと品位も備えており、両親もそれ以上は文句を言ってこなかった。二人がレオノーラに内緒でもう一着、〝王女らしい〟ドレスを仕立てさせていたことは知っていたけれど、結局それを見ることすらなかった。
エドガーのドレスを纏って社交界デビューを果たしたレオノーラは予想通りに――いや予想を遙かに超えて評判となり、喝采と共に社交界に受け入れられた。
エドガーもまたレオノーラのドレスを切っ掛けに、名を広く深く社交界に刻み、その翌年にはガドリン商会を代表する宮廷付き仕立て屋の地位を手に入れたのだった。
それからエドガーは、レイアドルという国が動かす、流行という名の巨大な時計の中心となった。
彼にドレスを仕立ててもらった貴婦人が社交界の中心となり、明くる週には同じデザインのドレスを誰もが着ている。そんな日々が続いた。
誰もがエドガーの作る衣装に熱狂し、たった二年の間にその名声は国中に響き渡ったのである。
エドガーはごく普通の平民で、そこもまた多くの国民から支持されるところだった。レイアドルにおいて、優秀な仕立て屋は限りない尊敬を集める。エドガーの国民からの人気は日に日に高まり、とうとう国王である父も放っておけなくなったようで、一代限りではあるが、爵位の授与をするに至ったのである。
そして現在、エドガーを前にレオノーラは息もできずにいた。
初めてあのドレスに腕を通した日から、ずっと彼に憧れ続けてきたのだ。
エドガーが仕立てたドレスのデザイン画は全て入手してきたし、実物が見たくて舞踏会や社交の場にも足繁く通った。
だが実際に彼の姿を見るのはこれが初めてだ。
初めてのドレスの仕立てでは直接会うことはなく、彼が〝宮廷付き〟になってからのこの二年も、レオノーラの担当にはならなかった。
エドガーを知る人から話を聞いて姿を想像してはいたが、こうして見る彼はその何倍も素敵だった。
――次は、私が彼に仕立ての担当をしてもらう番だわ。
その事を思い出し、レオノーラは踊り出したくなるのを必死に堪えて、胸の前で手を合わせた。
エドガーのドレスをまた着られることはもちろん、仕立てを口実に彼に会う機会が得られることが堪らなく嬉しい。
夢見心地で見とれていると、視線に気付いたとばかりにエドガーがこちらを振り返った。
レオノーラは王族の席に座っていたから、エドガーにもすぐに自分が誰か分かったはずだ。レイアドルただ一人の王女であると。
エドガーはこちらに歩み寄ると、まず王太子に挨拶をしてレオノーラに話しかける許可を得た。そしてレオノーラの前に恭しく膝を突き、頭を下げた。
「エドガー・ランハートです。レオノーラ王女殿下、お会いできて光栄です。この栄誉を賜る機会を、ずっと待っておりました」
まさか彼の口から『会いたかった』という言葉が出るなんて。
ずっとエドガーに憧れていたレオノーラにしてみれば、心臓が口から飛び出そうな程の衝撃だった。
しかし考えてみればおかしなことではない。エドガーにとって、レオノーラは成り上がりの切っ掛けになった人物だ。むしろ特別な思い入れがあって当然だろう。
込み上げる優越感に、余計なことを沢山喋ってしまいそうだった。
「私も会いたかった」とか、「あのドレスは今でも大切にとってある」とか、「あなたは想像よりずっと素敵だった」とか。
だがレオノーラはレイアドル王家の一員だ。
ひとりの仕立て屋を贔屓にすることは許されない。
レオノーラは話したいことを全て飲み込んで、出来る限り王女らしい笑みを浮かべた。
「初めまして、エドガー。社交界入りの時は素敵なドレスをありがとうございました。あのドレスはいまでも大切にとってあります。次の一年、私の衣服の仕立てをよろしく頼みます」
少し心の声が漏れてしまったが、まあ許容範囲だろう。
兄も不思議がってはいないし、きっと取り繕えているはずだ。
形式通りの台詞を口にできたことにほっとしていると、エドガーは僅かに眉をあげたあと、にっと口端をあげた。
「ええ、お任せください」
頷く彼の深い黒色の双眸は、美しさの裏で自信と野心をみなぎらせている。
その瞳をのぞきこんだ瞬間、レオノーラの心は大きく揺さぶられた。
エドガーは、レオノーラにとってまるで雷そのもののような男だった。
眩いほどに鮮烈で、レオノーラを夢中にさせてしまう。
離れて見ている分にはまだ良いが、いざ触れてしまえばこの心臓などひとたまりもない。
レオノーラはどうしようもなく、彼に恋に落ちてしまった。
だが、あまりに不毛な恋だ。
この初恋が実る日は絶対に来ない。
エドガーは貴族の位を得たとはいえ、一代限りで領地も持たない。
いくら国民から讃えられようとも、平民出身の仕立て屋にすぎないのだ。
かたやレオノーラは、生まれながらに義務と責任を負った王族の人間だ。
つい先日、隣国アナンテアの王太子と婚約が決まったところでもある。
そう、レオノーラは三年後の春には、かの国の王太子妃になることが決まっているのだ。
この恋は生まれた時から死んでいる。
――だけど……。
嫁ぐまでの間だけ、ひっそりと胸をときめかせるぐらいは誰も咎めないのではないか。
幸い、本心を隠すのは得意だ。だからきっと大丈夫。
レオノーラはそう自分に言い聞かせながら、慣れた微笑みを浮かべた。
「エドガー。私は三年後、アナンテアに嫁ぎます。……その時には、婚礼衣装を作ってくれますか?」
婚礼用のドレスは、王族が仕立て屋を指名できる数少ない機会のひとつだ。
レオノーラは彼の作ったドレスで嫁ぎ、それを脱いだ時に、この胸に抱えた想いを捨てようと決めた。
するとエドガーは、自信に満ちあふれた表情で頷いた。
「ええ、もちろん。殿下を世界で一番幸福な花嫁にしてみせます」
大国アナンテアの、王太子妃の花嫁衣装。それはまさにレイアドル一の仕立て屋に相応しい仕事だろう。
エドガーはその仕事を軽やかにこなし、さらに名声を高めるに違いない。
彼の頭にあるのはその野心だけで、もちろんレオノーラの想いに気付くことなどない。
そのことに、火で炙られたように胸がチリチリと痛んだけれど、レオノーラはおくびにも表情に出さなかった。
それからさらに三年の間、レオノーラはエドガーに焦がれ続けた。
彼のドレスを着る度に胸をときめかせ、その姿を垣間見る度に飛び跳ねたくなるぐらいに嬉しくなって、噂を耳にする度に誇らしい気持ちになった。
幸福な日々だった。
たとえ結ばれなくても、この想いを告げることすら許されなくても、エドガーのことを考えるだけで心が満たされた。
彼を想う時だけ、レオノーラは王女でなく、ひとりの人間になれた。
そう、幸福な日々だったのだ。
この思い出だけを糧に、これからの人生を送れると信じられるぐらいに。
レオノーラが十八歳になった年の春、王弟が反乱を起こし、この身に処刑が言い渡されるその瞬間までは――。
1章 王家の針と糸
エドガーにとってこの世の全ては、ただの線と色の集合体だ。
豚も人間も、その辺の石ころも変わらない。
そこに彼にとっての線引きがあるとすれば、それは〝エドガー・ランハートのセンスを理解できるか〟ということだけだ。
〝人間〟の多くは、そういう意味においてのみ、エドガーにとって価値のあるものだった。
そしてレオノーラ・レイアドルという女は、そういう意味において、エドガーにはよく分からない存在だった。
エドガーの店は王城からほど近い場所、いわゆるレイアドルの一等地にある。
客を出迎える店内にはシャンデリアが輝き、赤いビロードのソファが置かれている。壁に掛けられた絵やタペストリーはもちろん、カーテンのレールからドアノブに至るまで店内にあるものは全て最高級の品物だ。
さらに奥には約三十人が仕事をできる工房と、エドガー個人の仕事部屋がある。
「……で、何の用ですか?」
エドガーは仕事部屋の硬いソファに腰掛け、不機嫌を隠そうともせずに足を組んだ。
正面に座るのは、五十代半ばの、恰幅も頭髪の後退具合も気前のいい男。
エドガーが所属するガドリン商会の社長、オズミック・ガドリンだ。
「何度連絡してもお前が返事をよこさねえから、わざわざこうしてオレが来てやったんだろうが。このクソ野郎が」
「こっちは大口の仕事が消えて機嫌が悪いんですよ。あんたも商人なら、それぐらい察したらどうですか」
チッと舌打ちをして、オズミックの売り言葉を安値で買い叩く。
椅子を蹴り上げて暴れ出さなかっただけ褒めてほしいぐらいなのに、なぜかオズミックは額に血管を浮き上がらせた。
「相変わらずだな、エドガー。娼館に生まれて、ぼろ切れ同然にこき使われていたお前を見いだしてやったオレに対する恩はまるでないと見える」
恩は感じているが、そういうのを一々愚痴っぽく言葉にするのは人間が小さいと思う。
「……はあ、すみません。で、何の用ですか?」
オズミックに一刻も早く帰ってほしい一心で、エドガーはそう言った。
とはいえ今は相手にしたくないだけで、エドガーはオズミックが嫌いなわけではない。
彼はエドガーの最初の理解者だ。
だからどれだけ人間が小さかろうが、金に細かかろうが、輪郭が豚に近かろうが、心からオズミックを疎むことはこれからもないだろう。エドガーにとって、オズミックは価値のある人間だ。例えば彼が極悪非道の商人で、裏で人身売買を繰り返し、薬の密売に手を染めていたって、エドガーはオズミックを肯定するだろう。もちろんオズミックにそんな度胸はないし、十分稼いでいるので、わざわざ悪事に手を染める必要もないのだが。
反対に、どれほど愛情をそそがれようと、エドガーのセンスを理解しない人間はまるで価値がない。
それは例えばエドガーの母親のように。
「エドガー、お前は今、この国がどういう状況だか分かっているのか?」
「分かってますよ。王家でクーデターが起こって大変なんでしょう?」
そのせいで仕事が飛んだんだから、分かっていないはずがないだろうが。腹だけじゃなくて、頭にまで脂肪がついてるんじゃないのか? この薄らハゲ。
そんなささやかな悪口を飲み込んで、エドガーはもう一度舌打ちをした。
レイアドルはここ三百年、他国からの侵攻を受けたことがない。
だがそれは、ずっと平和であったという事ではない。
〝服飾文化〟という特殊な資産価値を持つレイアドルは、常に他国によって奪い合いの対象になってきた。特にレイアドルと国境の一部を接する二つの大国、アナンテアとマランツは長年の遺恨を抱える敵国同士であり、レイアドルはその二カ国間の戦いに常に翻弄され続けてきたのである。
レイアドルはまるで褒賞品のように、戦争に勝った方の属国となることで生き延びてきた。そしてここ五十年はずっと、アナンテアの属国として過ごしてきたのだ。
「マランツ派の公爵閣下が、陛下がアナンテアに国を売り渡そうとしているとイチャモンをつけて暗殺し、王妃と王太子もその折に起きた暴動で亡くなった。そして議会はそれを受け入れた。つまりマランツ国の軍事工作がレイアドルの中枢にまで浸透していて、まもなくアナンテアとの戦争が始まるってことでしょう」
「……分かってるじゃねえか」
「まあ、これでも宮廷付きなんでね」
王族はもちろん、貴族とも深い繋がりがあるのだから、ある程度の話は耳に入ってくる。
「……マランツが、アナンテアと戦争をおっぱじめる前にレイアドルに干渉してきたということは、今度の戦いではウチが戦場になる可能性が高い。すでに荷物を抱えて逃げ出している商人も少なくねえ」
まあそうだろうな、とエドガーは頷いた。
それだけマランツは次の戦争に本気なのだろう。レイアドルを押さえておけば、当然アナンテアへの攻撃ルートが増える。レイアドルの文化を破壊し、他国からの強い非難を浴びてでも勝ちたいと考えるほど、マランツも何か追い詰められているのだろう。
だが、そんなことは全てエドガーにはどうでもいいことだった。
「……で? オレに新しい陛下への服を仕立てろとでもいうつもりですか?」
エドガーは、俯きながら黒いくせ髪を手で乱した。
この様な事態の中、オズミックがわざわざエドガーを訪ねてきた理由が他に思い浮かばなかった。
新しく立った王は、前王の腹違いの弟で、エドガーは大変気に入られていた。彼が数年前に公爵位を与えられてからは毎月のように呼び出されて服を仕立てていたものだ。
だがエドガーにとって、あの男は道ばたの石ころにも劣る存在だった。
彼はエドガーのセンスを好んで仕事を依頼していたわけではないからだ。
エドガーを流行もの程度にしか見ておらず、用意したコートやベスト、愛人のドレスに一々物知り顔で注文をつけてくる。しかもその注文のセンスが悪いときているのだからどうしようもない。エドガーの一番嫌いなタイプの人間だ。
性格も享楽を好む、絵に描いたようなぼんくらで、エドガーは何度〝薄汚い豚は裸で餌でも食ってろボケ〟という言葉を飲み込んだかわからない。
だがオズミックは、エドガーの予想に反して首を横に振った。
※この続きは製品版でお楽しみください。








