【試し読み】夜伽役を命じられた没落令嬢は騎士王子との初恋に殉じたい
あらすじ
どうか一夜でいいから夢を見させて。――「夜伽役」を命じられた元伯爵令嬢シーラは、初恋の相手である元婚約者アランの元を訪れる。今はただの家庭教師でしかないシーラが王族であるアランと結ばれることはない。それならば歪な形でも初恋を成就させたいと夜伽役を引き受けたのだった。しかし、ただの夜伽役であるはずのシーラをアランは毎晩情熱的に求めてくる。「……また、今夜」――まるで恋人との別れを惜しむような甘いキスをアランから贈られ、シーラは瞳を潤ませる。ずっとこんな日々が続けばいいのにと願ってしまうほどの幸せを感じながら、自分は夜伽役でしかないのだと言い聞かせる。けれど、アランへの想いは加速していき……
登場人物
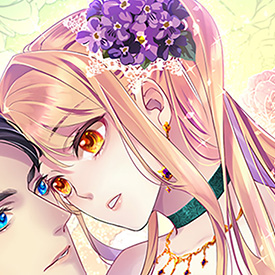
元伯爵令嬢。現在は辺境領の領主邸で家庭教師を務める。ある日、元婚約者の「夜伽役」を命じられ……

ファーレン王国の第二王子にして、シーラの元婚約者。辺境領にてシーラと再会し……?
試し読み
一章 運命の再会
雲一つない青空を琥珀色の瞳で見上げ、シーラは微笑みを浮かべた。温かな風が緩く結んだ栗色の髪をくすぐっていくのが心地いい。
ライト邸の庭園は春らしく様々な花が咲いており、とても美しい。
今日は外で勉強しようと提案したのは正解だったと自分を褒めたくなる。
「シーラ、これはこの綴りで正解?」
「見せてください。ええ、アリソン様。とっても素晴らしいです」
褒め言葉を口にすれば、教え子であるアリソンは嬉しそうに頬をほころばせた。自分を慕ってくれる少女のあどけない笑顔に、シーラは温かな気持ちになる。
ファーレン王国は領土の半分以上を森林が占める小さな国だ。主な財源は周辺諸国への材木輸出。木材を使った加工品の製造技術でも有名で、職人気質な国民性を誇っている。
森が豊かであるということは水源が豊富だという証でもあり、ファーレンの大地は長い歴史の中で何度となく戦を仕掛けられてきた。
この辺境領はそんなファーレンの国防の要だ。国境である深い渓谷を見下ろす領主邸は古く堅牢な造りをしており、外観はさながら一つの要塞のようであった。
だが一歩敷地内に足を踏み入れれば、そこは現領主であるライト伯爵の心遣いが隅々まで行き届いた温かで美しい場所だ。
今年で二十三歳になるシーラ・エクロイドは、この領主邸で家庭教師を務めている。
教え子は領主であるライト伯爵の一人娘、アリソン。先日十二歳を迎えたばかりの彼女は、明るい赤毛が印象的な愛らしい少女だ。
アリソンは幼い頃に母親を流行病で亡くした寂しさもあってか、シーラを姉のように慕い、懐いてくれていた。一人っ子だったシーラにとって、アリソンは大切な生徒である以上に愛しい存在だ。
「目上の方にお手紙を出すときは決して敬称を間違えてはなりませんよ」
「はぁい」
やる気のないアリソンの返事に、シーラは眉を下げる。
アリソンは優秀な生徒だが、のんびりとした辺境に育ったこともあり貴族社会の礼儀作法に対しての危機感というものが薄い。ほんの些細なやりとりのミスが、大きな傷になるというのが実感としてわからないのだろう。
「アリソン様。今はわからないかもしれませんが、いずれ王都で社交デビューをするのです。そろそろ、淑女としての嗜みを覚えてください」
「だって難しいんだもの。ねぇ、私がデビューするときはシーラも一緒に来てくれるんでしょう? シーラが傍にいれば安心だもの、大丈夫よ」
無邪気に微笑む少女の笑顔に、シーラはどう返事をすればよいかわからず、一瞬だけ言葉を詰まらせてしまう。
「……アリソン様。私は王都には行けません。だから、きちんと全部覚えてください」
「どうして? シーラは王都に住んでいたんでしょう? どうして私と一緒に行ってくれないの?」
不満と悲しさを瞳にたたえるアリソンの愛らしさに負けそうになりながら、シーラは困り果てたようなため息をこぼした。
(何も知らない彼女に、どう説明すればいいのかしら)
何を隠そう、シーラは六年前までは王都に暮らす紛れもない貴族の令嬢だった。
生まれ育ったエクロイド伯爵家は際だって裕福ではなかったが、歴史ある名家として誠実な領地運営に取り組み、領民たちからも慕われていた。
両親はお互いを想い合う理想的な夫婦で、一人娘のシーラはとても大切に育てられたと思う。
そんな幸せな日々に影が差したのは、十七歳のときだ。
最初の悲劇は母が落馬事故であっけなく命を落としたことだ。
その悲しみも癒えぬうちに、今度は父であるエクロイド伯爵が横領の罪で投獄されてしまう。身に覚えのないことだとエクロイド伯爵は訴えたが、信じてもらえず執拗な取り調べは数ヶ月に及んだ。
数ヶ月後。ようやく横領の真犯人はエクロイド伯爵の名を騙った別の貴族であると判明し解放されることになるが、一度失った信頼や時間、そして受けた傷はなかったことにはならない。
エクロイド伯爵は体を壊したことを理由に貴族籍を王家に返上すると、シーラと共に王都を離れたのだった。
王都を離れたあとは気ままな旅暮らしをしていた二人だったが、いつまでも根無し草というわけにはいかないことはわかっていた。
そんな矢先、手を差し伸べてくれたのが他でもないライト伯爵だった。古い友人の危機を知ったライト伯爵は、ずっと二人を探してくれていたのだ。
領内に屋敷を用意してくれたうえに、シーラに家庭教師という職まで与えてくれた。
『アリソンはお転婆でね。シーラのような淑女が傍にいてくれると私も心強い』
ライト伯爵の心遣いに、シーラは救われた思いだった。
幸いにもアリソンとは顔合わせのときから仲良くなれ、今では本当の姉妹のように過ごせている。
父もまた、この静かな辺境の暮らしが体に合っているらしく、王都を離れたときに比べて随分と体調もよくなった。
華やかな王都とは違い、素朴で穏やかな空気がシーラは大好きだった。この大地を故郷と思って生きようと決意し、何があっても二度と王都には戻らないと誓った。
だからいくらかわいい生徒のおねだりでも、王都に付いていくことはできない。
「アリソン様がデビューする頃、私はもうここにはいないかもしれないでしょう?」
「どうして? もしかして、お嫁に行ってしまうつもり?」
「……どうでしょう?」
曖昧に微笑めば、アリソンは納得できないわと頬を膨らませる。
「さ、お喋りはここまでです。授業の続きをしましょう」
少々強引に話を切り上げ、止まっていたペンを動かすように指示をする。
不満そうではあったが、アリソンは素直に机に視線を戻してくれた。
(ごめんね、アリソン)
申し訳ないと思いつつも、シーラは願わずにはいられない。
どうかこの穏やかな時間が永遠に続きますようにと。
だが、その願いはあっけなく壊されることになってしまう。
「視察、ですか?」
シーラは何度も大きく瞬き、目の前の二人を交互に見つめた。
授業を終え、自室に帰ろうとしていたところを執事長であるヘイデンに呼び止められたシーラは、領主の執務室に来ていた。
目の前にはライト伯爵が優しい笑みを浮かべて座っており、その横にはヘイデンが苦虫をかみつぶしたような顔をして立っている。
ライト伯爵は年の頃は父とそう変わらないはずだったが、現役で領地を治めていることもあってか随分と若く見える。白いものが混じり始めた焦茶色の髪をきっちりと上げ、恰幅のいい体躯を仕立てのよい服に包み、ゆったりとソファに腰掛けている姿は、まさに辺境の主にふさわしい風格だ。
対するヘイデンはどこか卑屈そうな外見をしている。長く伸ばした灰色の髪を一つに結び、肉付きの薄い体をやけにまっすぐに伸ばして立っている。年齢は伯爵より十は若いはずなのに、下手をすればシーラの父ほどの年齢に見えることもあった。服装や身につけている装飾品はそれなりに金をかけているとは感じるが、どこか浮いた印象が否めない。
対照的な二人ではあったが付き合いはとても古いらしく、ライト伯爵はヘイデンを深く信頼している。その証に、ヘイデンは屋敷における様々な権限を与えられていた。
シーラはどうして自分がここに呼ばれたのか、いまだにわからず戸惑っていた。
ヘイデンは頬を神経質そうに引きつらせながら、苛立たしげに足を揺らしていた。
「王都から視察団がやってくるとの知らせが届きました」
「まあ」
王都という言葉に胸の奥が痛みを訴える。
まさに先ほどアリソンと話したばかりだったこともあり、まるで誰からか見張られているようだという居心地の悪さを感じてしまった。
ライト伯爵はそんなシーラの機微に気がついたのか、気遣わしげな笑みを浮かべ「心配するな」と声をかけてくれた。
「視察といっても特別なものではない。どうも各領地を順番に回っているようなんだ」
「しかし、あまりに急ではありませんか」
ライト伯爵の言葉に反応したのはヘイデンだ。
「王都からの使者を迎え入れるのであればそれなりの準備が必要です。それなのに明日には到着するだなんて……」
「仕方あるまい。予告された視察では本質がわからぬと考えているのだろう。もてなしも不要だという指示だ。私たちはいつも通りに過ごしていればいい」
「ですが……」
納得がいかない様子のヘイデンがライト伯爵に食い下がっていたが、シーラはそれどころではなかった。
(知っている方がいたらどうしましょう)
逃げるように王都を離れたシーラにとって、過去の知り合いは顔を合わせたい存在ではない。気を遣われるならまだいいが、下手に絡まれるのは面倒だ。なにより、知りたくもない話を聞かされてしまう可能性もある。
(王都のことはなるべく耳に入れないようにしていたのに)
ライト伯爵はシーラが抱える苦しみに気がついているのだろう。だからこそ、事前に知らせてくれたに違いない。
「シーラ、君はアリソンといつも通り過ごしてくれ。なんなら別荘に行ってもらってもいい。視察団も君にまで何かを聞くようなことはないだろうから」
「……ご配慮、感謝します」
優しい気遣いに胸が熱くなる。
シーラが王都に置いてきた過去を知っているからこそ、ライト伯爵はそう言ってくれているのだろう。
「別荘には行かず、ここでいつも通り過ごしたいと思います」
「だが……」
「アリソン様を連れて急に別荘に行ったなどと視察団の方に知られれば、伯爵様に妙な疑いがかかるかもしれません。そんなのは嫌です」
大切な人があらぬ疑いをかけられ苦しむ姿は二度と見たくない。そんな決意のこもったシーラの顔に、ライト伯爵は切なげな微笑みを浮かべる。
「ありがとうシーラ。極力君に負担がかからないように配慮しよう」
もう一人の父と言っても過言ではないライト伯爵の言葉にシーラは静かに頷いた。
「……」
ヘイデンだけは何故こんな小娘にそこまで気を遣うのか納得していない表情でシーラを睨み付けてきていた。
今のシーラはただの家庭教師だ。
本来ならば雇い主と使用人として関係を律しなければならないところだったが、ライト伯爵はシーラのことをいつも気にかけ、まるで実の娘のように扱ってくれていた。
事情を知らないヘイデンにとってみれば、家庭教師の分際で主人と親しげに会話をし、特別に配慮されるシーラが気に食わないのは仕方がないことだろう。
(そろそろ、ここを離れるべきなのかも)
もうあれから六年が過ぎた。
過去を忘れ、新しい人生を生きるときがきたのかもしれない。
ライト伯爵の庇護下で生きていれば、今回のように王都から誰かがやってくるかもしれない。そのとき、相手がシーラを知っていたら。そう考えると、体が自然と震えてしまう。
せめてアリソンが社交界デビューする日が決まるまではここにいたかったが、潮時なのだろうか。
こみ上げてくる切ない想いを押し殺すように、シーラは小さな拳をぎゅっと握りしめた。
*
翌日、予告通りに視察団が領内に入ったとの知らせが届いた。
出迎えの準備に、領主邸は大騒ぎだった。
といっても滞在するのは数名だけ。
だが、人を出迎えることに不慣れな使用人たちはどこまで準備をすればいいのかわからなかったのだ。シーラも過去の記憶をたよりに彼等を手伝った。
出迎えに向かったライト伯爵が、視察団を伴い帰ってきたのは、夕刻になってからだ。
茜色に染まった玄関前の広場で、シーラはアリソンに付き添っていた。
本来ならば出迎えに立つつもりはなかったのだが、アリソンのおねだりには勝てなかったのだ。
「ようこそ我が城へ」
芝居がかった口調と仕草のライト伯爵の立ち振る舞いに、アリソンたちが笑い声をあげた。とても和やかな空気に包まれていく。
だが、シーラだけは笑えずにいる。
心臓が痛いほどに大きく脈打ち、その場に立っているのがやっとだった。
「世話になる」
視察団の先頭に立ち、低く少しだけかすれた声をしたその人は、感情の読めない静かな顔をしている。
(アラン様)
最後に会ったときからずっと成長していたが、それが誰なのかすぐにわかった。
大柄なライト伯爵に並んでも見劣りしないほどの長身と、甲冑に包まれていてもわかる鍛え上げられた肉体。艶やかな黒髪に彩られた精悍な顔立ち。そして、透き通るような青い瞳をたたえた切れ長の目元。
アラン・ファーレン。
このファーレン王国の第二王子にして、シーラの元婚約者。
(どうして)
この場から逃げ出さないようにするのがやっとだった。
アランの青い瞳が、使用人たちの顔を覚えるようにゆっくりとこちらに向けられるのがわかる。
(っ……)
間違いなくぶつかった視線に気を失いそうだった。
瞳の奥が痛みを訴え、涙が滲む。
心と体が、まだアランを忘れていないことを必死に訴えている。
だが、アランの表情に変化はない。
無感動な瞳はすぐにライト伯爵に戻される。そして何ごとかを話しながら、二人はシーラたちの前を通り過ぎ建物の中に入っていった。
※この続きは製品版でお楽しみください。








